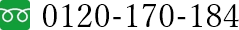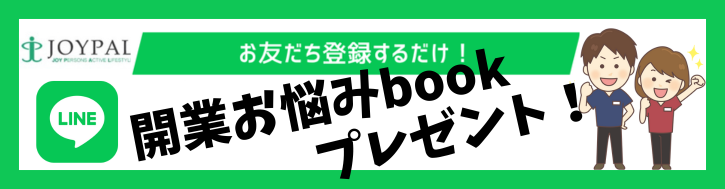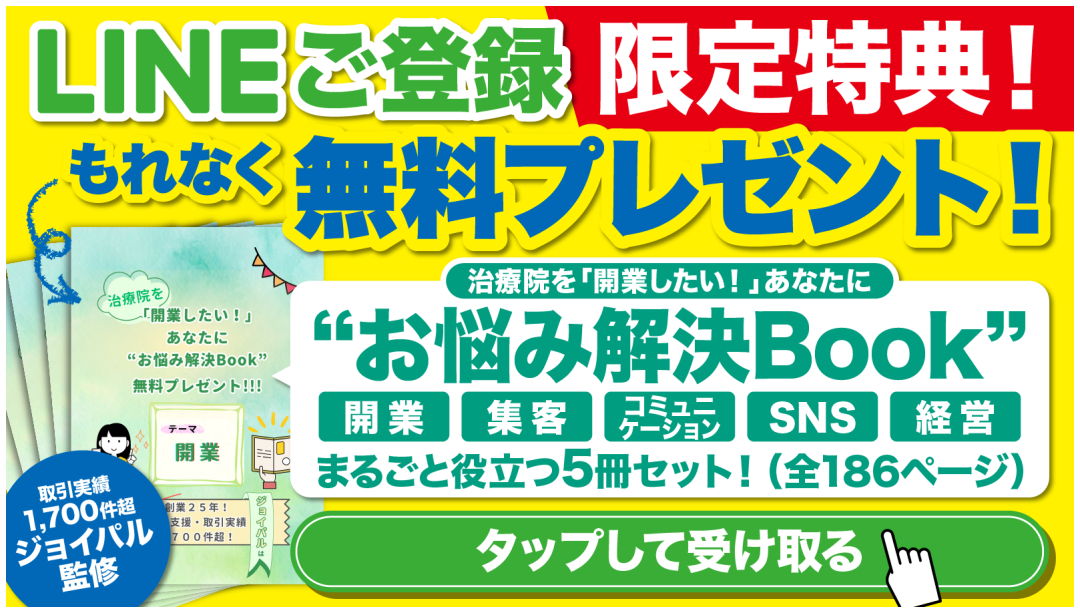公開日:2025年08月19日 ![]()
整骨院や接骨院を開業するとき、つい施術技術や内装ばかりに目がいきがちですが、実は「制度や請求のルールを理解しておくこと」が長く経営を続けるために欠かせません。療養費の請求ルールを知らずに手続きを誤ると、不正請求とみなされてしまうケースもあり、最悪の場合は返還命令や行政処分につながるリスクもあります。
本記事では、整骨院の開業を目指す方に向けて「整骨院で不正請求になるケース」や「保険が使える施術の範囲」をわかりやすく解説します。
整骨院で不正請求になる5つのケース

接骨院・整骨院では、正しい範囲で保険を使うことが大前提ですが、以下のようなケースは不正請求にあたります。
-
部位転がし
-
施術箇所の偽造
-
施術部位や日数の水増し
-
受傷理由の改ざん
-
柔道整復師以外の施術を保険請求
これらはすべて、療養費制度の趣旨に反する不正行為とされ、発覚すると厳しい処分や返還命令の対象となります。
部位転がし(施術部位を次々変えて通院を引き伸ばす)
「部位転がし」とは、同じ患者さんの施術部位を短期間で次々と変え、通院を長引かせる行為です。結果として必要のない施術が繰り返され、療養費が不正に発生してしまいます。
故意でなくても「まだ治っていないのに別部位の施術を始める」と、部位転がしに該当する可能性があるため注意が必要です。
詳しくは、厚生労働省が出している資料「柔道整復の施術に係る療養費関係」が参考になります。
施術箇所の偽造(実際と違う部位を請求)
患者さんには肩の施術を行ったのに、レセプトには腰の施術として記載するなど、実際と異なる部位を請求するケースです。本来は自費となる施術を、保険が使える施術として偽る場合にも当てはまります。
この場合は、「実際より多くの療養費を請求する行為」として不正請求に該当するため、注意しましょう。
施術部位や日数の水増し
本来必要な部位以外にも施術を行い、複数部位を請求するケースです。例えば、「肩の打撲に加え、首や背中も施術したことにして3部位で請求する。」などが該当します。
また、患者さんが来院していない日を「来院した」として請求する「日数の水増し」も不正行為にあたります。
受傷理由の改ざん(慢性症状を急性外傷に書き換える)
肩こりや腰痛といった慢性症状は保険適用外ですが、これを「打撲」「捻挫」と偽って請求するケースがあります。
本来の制度趣旨に反するため、明確な不正請求とされます。
柔道整復師以外の施術を保険請求する
保険請求できるのは、柔道整復師が行った施術のみです。
資格のない整体師やアルバイト、学生が施術を行い、柔道整復師の名前で請求することは不正にあたります。
接骨院・整骨院で保険が使える施術の範囲

接骨院・整骨院では、健康保険を利用できる施術と、できない施術があります。
この違いを正しく理解しておかないと、意図せず不正請求につながるおそれがあるため注意が必要です。
保険が使える施術
健康保険の対象となるのは、急性または亜急性の外傷性のケガです。具体的には次のような症状が当てはまります。
-
骨折
-
脱臼
-
打撲
-
捻挫
-
挫傷(筋肉や腱の損傷)
これらは、スポーツや日常生活、事故などで突然発生するケガが対象となります。
なお、骨折や脱臼の場合は、応急手当を除き医師の同意が必要です。詳しくは、厚生労働省の「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」を参考にしてください。
以下の記事も参考になります。
整骨院は医療機関ではない?健康保険との関係や開業前に知っておきたいこと
保険が使えない施術
一方、次のような慢性的な症状や疲労に対する施術は、健康保険の対象外です。
-
慢性的な肩こりや腰痛
-
疲労回復やリラクゼーション目的のマッサージ
-
加齢による体の痛みや不調
これらは自費診療となり、保険を使って請求することはできません。
受領委任払い制度について
整骨院・接骨院では「受領委任払い制度」が採用されています。これは、患者さんが窓口で自己負担分(1〜3割)を支払い、残りを保険者が柔道整復師に直接支払う仕組みです。
この制度があるからこそ、整骨院で保険施術がスムーズに受けられる一方で、不正請求が問題になりやすい背景ともなっています。
整骨院で不正請求が発覚すると?
接骨院・整骨院で不正請求が発覚すると、院にとって大きなダメージとなります。「知らなかった」では済まされず、金銭的・社会的な責任を同時に負うことになります。主なリスクは以下の通りです。
-
療養費の返還命令(過去分までさかのぼる場合あり)
-
行政からの処分や指導(業務停止・契約解除など)
-
刑事責任を問われる可能性(詐欺罪など)
-
患者や地域からの信頼を失い、経営が成り立たなくなる
それぞれ、詳しく解説します。
療養費の返還命令
不正請求が確認されると、該当する療養費はすべて返還しなければなりません。
場合によっては1年分以上の請求が調査対象となり、数百万円規模の返金命令が出ることもあります。
経営に直結する資金が一気に失われるため、最悪の場合は廃業に追い込まれる可能性もあります。
行政からの処分や指導
厚生労働省や保険者(保険組合など)から指導を受けるほか、悪質な場合は業務停止命令や受領委任契約の取り消しといった処分につながります。
受領委任契約が取り消されると、以後は整骨院で健康保険を扱うことができなくなり、経営モデルそのものが崩壊します。
刑事責任を問われる可能性
明らかな不正請求は「詐欺行為」とみなされ、刑事事件として立件されるケースもあります。
その場合、詐欺罪での起訴 → 罰金刑や懲役刑といった刑事罰に発展する可能性があります。
経営者や施術者個人の社会的信用も大きく失われます。
患者や地域からの信頼を失う
不正請求のニュースや噂が広がれば、患者離れが起こります。
「お金目当ての整骨院」というレッテルを貼られれば、新規患者が減るだけでなく、長年通っていた患者さえ離れていきます。
地域密着型である整骨院にとって、信頼の喪失=経営存続の危機に直結します。
不正請求を防ぐためにできること

不正請求は「うっかり」でも発生する可能性があります。
接骨院・整骨院で正しく保険請求を行うために、以下のような対策を実践しておくことが大切です。
-
請求ルールや制度をスタッフ全員で共有する
-
レセプト内容と施術実態を必ず一致させる
-
定期的に外部の研修やセミナーで学ぶ
-
迷ったときは必ず保険者や組合に確認する
それぞれ、解説します。
請求ルールや制度をスタッフ全員で共有する
柔道整復師だけでなく、受付スタッフや事務担当者も制度を理解しておく必要があります。
保険が使える範囲や請求の仕組みをマニュアル化し、日常的に共有しておくことで、思わぬ不正を防ぐことができます。
レセプト内容と施術実態を必ず一致させる
施術した部位・回数・日数は、カルテとレセプトに正確に記録することが原則です。
「ちょっとぐらい」と軽視してしまうと不正請求につながるため、必ず施術内容と請求内容を照合する仕組みを作りましょう。
定期的に外部の研修やセミナーで学ぶ
療養費の請求ルールは、厚生労働省や保険者の方針によって改定されることがあります。
定期的に団体や協会の研修に参加し、最新の制度をキャッチアップすることが、不正を未然に防ぐポイントです。
迷ったときは必ず保険者や組合に確認する
判断に迷うケースでは、自己判断せずに必ず保険者や組合へ確認することが重要です。
「これぐらいなら大丈夫」と曖昧に処理すると、不正請求とみなされるリスクが高まります。
整骨院の正しい経営と開業相談はジョイパルへ
接骨院・整骨院での不正請求は、意図的でなくても「部位転がし」「施術内容の偽造」「水増し請求」などで発生してしまうことがあります。
不正が発覚すると返還命令や行政処分だけでなく、地域の信頼を失い、経営そのものが立ち行かなくなる大きなリスクがあります。
だからこそ、開業を考えている方は、最初の段階から 「正しい制度理解と運営体制づくり」 が欠かせません。
ジョイパルでは、これまで1,700件以上の整骨院・接骨院の開業支援を行ってきました。
資金調達や内装設計、集客支援はもちろん、療養費請求のルールや経営上の注意点まで、トータルでサポートしています。
開業を目指す方は、まずは開業の流れや必要な手続きを押さえたうえで、柔道整復師の資格要件を確認し、事前にしっかり準備を進めることが大切です。
また、実際に必要となる開業費用の目安や、利用できる助成金・補助金制度も併せて検討すると安心です。

「安心して開業したい」
「長く信頼される整骨院をつくりたい」
そんな方は、ぜひジョイパルにご相談ください。